悩み(ゆうとママさん:3歳のお子さん)
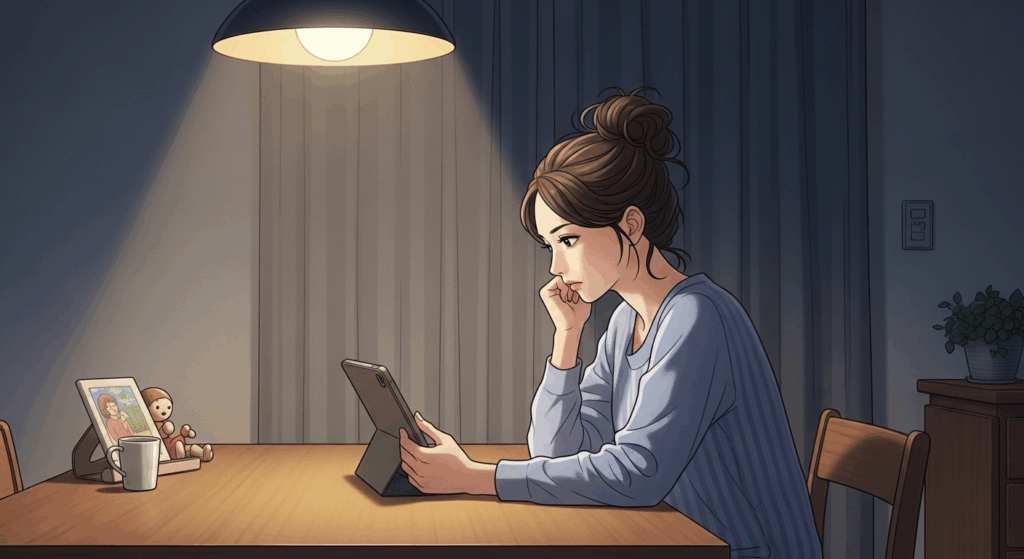
「これまで子どものIQについて深く考えたことはありませんでした。ですが、今後の支援や就学を考えた時に、客観的な目安として検査が必要になるのであれば、受けさせておいた方が良いのかと悩んでいます。
何歳ごろから受けられるのか、またどんな種類の検査があるのかも分からず、どこに相談すれば良いのか分かりません。」
体験談・アドバイス
れんさん(小学生のお子さんを持つ)
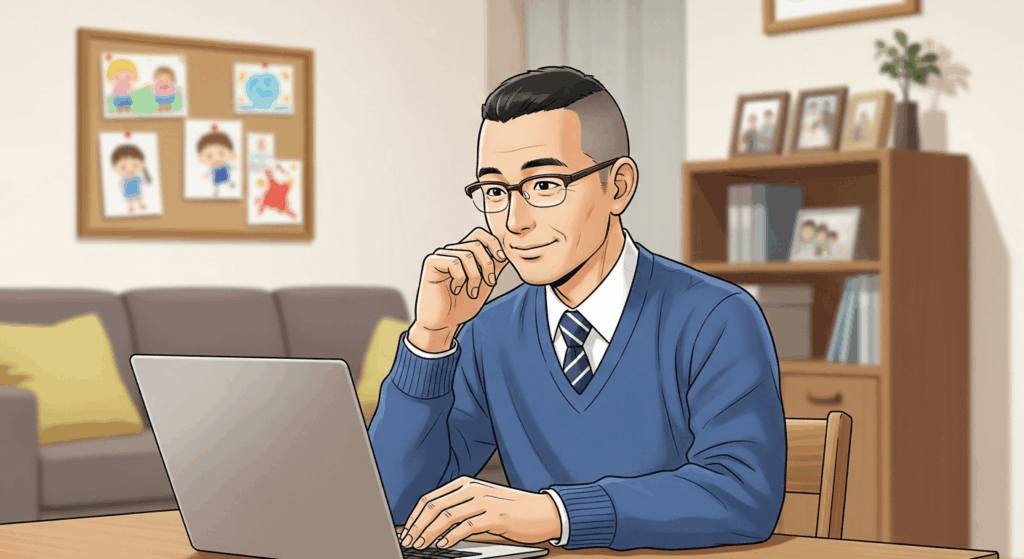
「うちの子は4歳の時に『田中ビネー知能検査V』という検査を受けました。確か、この検査は2歳から受けられるものだったと思います。その後も、就学前の検診や療育手帳の更新の際に、何度か知能検査を受けています。
ただ、検査を受けるかどうか、またどの検査を受けるかという判断は、病院や先生の方針によって本当に様々だと感じます。
以前、うちの子の主治医は『ウィスク(WISC)検査はまだ必要ない』という方針でしたが、先生が変わったら『受けた方が良い』と言われました。また、支援級のお友達は、病院を変えた途端に『なぜ今まで一度もウィスクを受けていないの?』とすぐに検査してもらえた、という話も聞きます。
実は私も、最初にかかりつけの小児科に相談した時は『必要ない』と言われました。ですが、別の場所で保健師さんに相談したところ、『一度専門の方に』と行政に繋いでくれたんです。そこでも『考えすぎですよ』と一蹴されてしまい、納得できずにその日のうちに自分で療育センターに電話をかけました。専門家の中でも意見が違うことは少なくないので、親が納得できる場所を探すことが大切だと感じています。」
補足ポイント
検査を受けられる年齢や種類
知能検査にはいくつか種類があります。例えば「田中ビネー知能検査」は2歳から成人までが対象で、比較的低年齢から受けられるのが特徴です。一方、世界的に広く使われている「ウィスク(WISC)式知能検査」は、一般的に5歳から16歳が対象です。お子さんの年齢や状態によって、どの検査が適切かは変わってきます。
検査の目的とは?
知能検査の目的は、単にIQという数値を知ることだけではありません。検査を通して、お子さんの得意なこと(認知的な強み)と苦手なこと(弱み)を客観的に把握し、今後の療育や学習の支援計画を立てるための重要な手がかりを得ることにあります。また、就学相談や療育手帳の申請の際に、検査結果の提出を求められる場合もあります。
専門家による方針の違い
体験談にもあるように、知能検査に対する方針は、医師や相談する専門家によって大きく異なるのが実情です。かかりつけの小児科医が必要ないと考えても、発達の専門医は検査を推奨する、といったケースは珍しくありません。
信頼できる相談先を見つける
もし検査を受けるべきか迷ったら、まずはお住まいの自治体の発達相談窓口や、通っている療育施設のスタッフに相談してみましょう。複数の専門家の意見を聞きながら、ご自身が「この先生になら任せられる」と信頼できる相談先を見つけることが、何よりも大切です。
まとめ
お子さんの知能検査を受けるかどうかは、ご家庭や医師の方針によって様々です。大切なのは、検査を「子どもを評価するためのもの」ではなく、「子どもの特性を深く理解し、より良いサポートに繋げるためのツール」と捉えることです。
専門家によっても見解が分かれることがあるため、一つの意見だけで判断せず、複数の情報を集めてみてください。そして、保護者として納得のいく説明をしてくれる、信頼できる専門家と一緒に今後のことを考えていくのが良いでしょう。

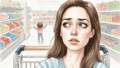

コメント